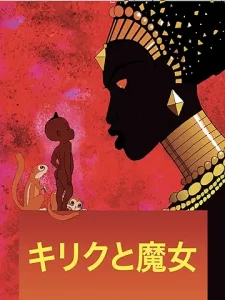シネマの宝石学
―洗練された大人のおとぎ話23
宝石ずくめの魔女とスーパー赤ちゃんの戦い
幸運は、あるとき突然、訪れる。たとえば、私にとっては、この映画と遭遇した瞬間もそのひとつである。深夜、BSで、何気なく始まった映画。なんの意識もしていなかったが、みっつめのせりふが聞こえてきたときには、すでに、この映画は只者ではないと気がつき、引き込まれてしまった。映画のなかのアフリカの村。この村にとっての幸運は、キリクという赤ん坊が生まれたことだった。彼らは、それに気がつかなかったけれど・・。そして、魔女にとっても、キリクと出会ったことが、大きな幸福となる。
「キリクと魔女」は、この連載で初めて取り上げるアニメーション映画だ。宝石をまとった優雅な魔女と、裸の赤ちゃんが戦う物語。舞台は、アフリカのとある村。いつか読んだアフリカの神話世界がこの映画のなかに息づいている。月足らずで生まれたあかんぼう、ロボットみたいな魔女の手下、深い智慧をもった山の賢者。すべては、象徴的で、この世の真実を伝えている。短いせりふが印象的で、この世がどういう仕組みでできているか、人間はどんなふうにできているか、この小さな村の小さな出来事がすべて教えてくれるのだ。素直に「なぜ」を連発して、最高の幸せを手に入れたキリクのように、私も子どものころに戻って、すべての疑問を「なぜ」と、問い直してみたくなる。そのとききっと、奇跡が起きるのだ。
原作・脚本・監督は、フランス人のミッシェル・オスロ。幼少期を過ごしたアフリカ・ギニアの強烈なイメージが、この映画をつくる深い原動力となったという。素朴派の画家ルソーの名画を思わせる、色美しいアフリカの景色。目を射るほど赤い火炎樹の並木や、一面、青と白で織りなされる眩い花園、イボイノシシやヤツガシラ、地中で暮らすリスなど、アフリカの大地に息づく野生動物たち。セネガル生まれの世界的大歌手ユッスー・ンドゥールの手による音楽―村人たちの歌と踊りや魔女のテーマ―が、土俗的な魅惑の世界にいざなってくれる。行ったこともないのに…アフリカの熱気が、なつかしく肌を刺す。人類の起源は、アフリカにあり。そんな学説を思い出す。
この映画は、1998年に製作され、世界中で人気を博し、数々の賞を受賞した。日本では、2004年、スタジオジブリにより日本語版が公開され、話題となっている。キリク役は、名子役神木隆之介君、魔女のカラバは浅野温子が扮し、ぴったりの配役。また、「火垂るの墓」などを監督した高畑勲が翻訳を担当。その倒置法のせりふが、この映画をより神話的に感じさせる。一方、フランス語版のほうは、声優をアフリカ・セネガル人が務め、アフリカの濃密な空気をびんびん伝えてくれる。
生まれたときから自立しているベイビー
「かあさん。僕を生んで」このアニメの最初のせりふだ。その声は、女の人のお腹から聞こえた。「おなかのなかで話しかける子は自分で生まれるの」母は静かな声で告げた。赤ちゃんは自分の力で誕生する。月足らずで生まれた小さな子どもは、「僕の名前はキリク」と、高らかに名乗った。「かあさん、僕を洗って」と頼み、「自分で生まれた子は自分で洗うの」と母に言われたキリクは、じゃぼんとおわんに飛び込み、機嫌よく、自分で、産湯を使う。人生の最初の瞬間から、自立している子どもなのだ。母は彼に、水を無駄にしてはだめ、と注意する。泉の水は、魔女が干上がらせてしまったから。「ぼくのとうさんはどこにいるの?」 母は答える。「魔女に食べられてしまったの」 「とうさんの兄弟は?」「男たちは、みんな魔女のカラバと戦いにいった。そして魔女に食べられてしまったの」 村に残ったのは、女と子どもと老人だけ。村人の財産もすべてとりあげられてしまい・・ここは、魔女に呪われた村なのだ。
せっかく誕生したというのに、待っていたのは、最悪の環境だった。しかし、キリクは底抜けに明るい。赤ちゃんという存在は、いつだって陽気なものだ。幸福も不幸も知らず、現状を100パーセント受け入れられるからだろう。どんな苦難の中で生まれたとしても、暗い顔の赤ちゃんなんて、想像できない。キリクだって、その意味では、ごく普通の赤ちゃんなのだ。男たちの中で、かあさんの末の弟がたったひとり生きており、これから魔女退治に出かけるという。「ぼく手助けにいくよ」と元気に外に飛び出した。キリクは、生まれたばかりだけど、とてつもなく早く走れる。さすが、スーパー赤ちゃん。小さいキリクの、試練続きの人生、冒険に次ぐ冒険の日々が今、始まったのだ。
宝石で着飾った魔女
「恐れ多きご主人さま。男が来ます」魔女カラバに注進したのは、手下の呪い鬼だった。魔女は村外れの藁の家に、呪い鬼たちにかしずかれて暮らしている。「男」とは、キリクの若い叔父さんだ。気はいいけど、とくに優秀というわけではない叔父さんの頭の上で、キリクは帽子の中に隠れ、代わりに、魔女と駆け引きをした。この日の結果は、引き分け。これが魔女との出会いだった。「ぼくはキリクだ。どうしてお前は意地悪なのか」一番聞きたい質問を本人にぶつけてみた。魔女は、それには答えない。「お前を食べてやりたいが、あんまり小さすぎて、その気にならぬ」村を不幸に陥れる、邪悪な魔女カラバ。働き盛りの男たちを食べ、村の黄金をすべて奪い、命の源である泉を枯らした極悪非道の女。彼女は蛇使いでもある。
しかし、カラバは、とてつもなく美しかった。悪意と権力に満ち、そして、優美な女だった。村の者たちが、子どもは裸、大人も腰巻ひとつなのにくらべ、カラバはまぶしいほどゴージャスで、威厳に満ちている。宝石ずくめの、輝ける魔女。王冠のように結われた黒髪には、宝石を金の星のようにちりばめ、首は黄金の筒で覆い、イヤリングにネックレス、バスト飾り、バングルが、褐色の肌に、なんてきらきら輝いていることだろう。スタイル抜群で、整った顔立ち。その黄金のきらめきに、ブルー系の凝ったプリントのスカートが良く映える。
カラバは男たちを憎んでいた。女たちを軽蔑していた。そして子どもを嫌っている。なぜなのだろうか。キリクは、そのわけを知りたかった。魔女がどうして意地悪なのか、出会う人みんなに確かめるのだが、誰も知らない。彼らはただ恐れるだけなのだ。その問いに答えられるのは、キリクの祖父に当たる山の賢者だけだ、と母がいった。しかし、その賢者に会うためには、魔女の家を通り越していかなければならない。無事、そこを通れたとしても、山の入り口には、大アリ塚がそびえ、山の賢者に会う価値のないものには、とびらを開かないのだという。祖父に会いたい。それこそがキリクの、最大の試練だった。
やがて、キリクは知ることになる。彼女が意地悪になった秘密を。それはとてつもなく、つらく、苦しい秘密だった。その秘密は、彼女が美しいことと、関係があるかもしれない。カラバは、家庭の幸福とは対極のところにいる女だった。キリクたち子どもに手を出したくても、彼らが、村に帰り、母親のところにいると、何もできないのだ。この事実は、魔女の秘密をとくひとつのカギだと思う。その秘密を知ったとき、キリクは、村を救う手立てを見つける。それは、魔女カラバにとっても開放のときだった。
彼女の手下、呪い鬼たちも、この映画の見所となっている。「災いあれ。お前たちに、ひとつでも金の塊を残すならば」呪い鬼たちは、こういって、村人たちを脅す。そして、金のくちばしをした呪い鬼が、黄金のありかを探るのだ。隠された黄金が見つかると、今度は、ホースのような口をした呪い鬼が、火炎放射器となって、隠した家を焼き尽くす。キリクや村人を監視している見張り役は、カラバの家の屋根の上で、巨大な目をぎょろぎょろさせている。呪い鬼は、その役割により、さまざまな形をしているのだ。
英雄の条件
生まれたばかりの頃から、キリクの活躍は目覚しかった。初めに、子どもたちを救った。魔法にかかり、猛スピードで走る丸木舟や、人間を捕らえる美しい樹木から、子どもたちを脱出させ、魔女の手に落ちるのを、阻止したのだ。次に、呪われた泉の秘密を突き止め、たったひとり、命を賭けて、泉の水を村人たちに取り戻した。
ついには、魔女の秘密を教えてもらうため、山の賢者に会いに行こうとする。最後の冒険は、とりわけ危険で、孤独で、無謀な試みだった。地面の下の真っ暗な迷路をたどり、スカンクのような動物や、イボイノシシに襲いかかられ...しかし、キリクはひるまない。自分だけの勇気と才覚で、迷いながらも乗り切っていく。ひとつひとつの試練が、彼を普通の赤ちゃんから、英雄へと、成長させていった。
ついに、大アリ塚の前に立つ。資格のないものは通さない関所。そのアリ塚は・・・開いたのだ。彼の勇気と才知をたたえるかのように。山の賢者の住む国は、かっこいい鳥たちに護衛され、神の存在を感じさせる異界だった。ここまでやっと辿り着いたとき、キリクはまぎれもなく、ひとりのヒーローとなっていた。どうしてこんなことができたのだろう。キリクは、普通以上に小さな赤ん坊だ。空を飛べるわけでもなく、動物と話ができるわけでもない。後半は、母から父の形見の短剣をもらうけれど、それまでは、裸一貫だったというのに。
彼が、人よりすぐれているのは、走るのがとても速いこと。それだって、長く走ると疲れてしまう。しかし、彼には勇気があった。自分が何とかしなければという自立心があった。それに加え、先入観を何も持たず、物事をまっすぐ見ることができる、純粋さがあった。それらが直観となり、彼の行く手を助けるのだ。
それにしても、彼がこんな風に自分の判断を信じ、勇敢に戦えたのは、母の支えがあったからだろう。クールでいながら、愛情深い母も、物事を真直ぐ見られる人だった。お山の賢者に会いに行く前、例によって「魔女はどうして意地悪なの?」と聞くキリクに、母は「それは魔女だけじゃない」と答えた。「意地悪な人はいる。こちらはなにもしていないのに。水はぬらし、火が燃えるのと同じことなんだよ」 「必要なことは、覚悟していることだね」とキリク。大切なのは、覚悟していること。英雄とは、覚悟している人なのかもしれない。
キリクは、魔女との最後の対決に際し、覚悟した。目的を全うできなければ、死ぬのだと。彼の戦いは、最初から、いつもたったひとりで孤独だった。村人を初めとする大衆は、無責任に、運命を嘆き、助けてもらっても、あっという間に忘れ、いいたい放題いっているけれど、英雄は違う。試練は次々現れるので、日々、成長していなければ、倒れてしまうかもしれない。それは、どれほど孤独なことだろう。その孤独は、優しい母でさえ、どうすることもできない。
祖父である賢者と堂々と話をしたあと、「ひざの上にあがってもいい?」と聞き、賢者のひざに抱かれたとき、キリクは、つかの間、小さな子どもに戻って、少しだけ休息した。「時々僕、少し疲れてしまうんだ」「戦うときは、何時も一人だから」そうして、ほんの少しだけ甘え、最後の戦い、カラバとの対決へと、出かけていった。
英雄とは、かっこよく、飛びぬけて優れた特別な人と思っていた。しかし、私たちが生まれる瞬間から見ているキリクは、村人たちに「ちびっこいねえ」といわれ、彼らを救っても救っても、馬鹿にされたりするほど小さい子どもなのだ。その赤ちゃんが、これだけのことを成し遂げるなら、私にも何かできるかもしれない。この映画は、見る人にとてつもない勇気を与えてくれる。
物語の結末は、とても意外で驚かされる。それは映画を見てのお楽しみだが、これだけは書いておきたい。数々の経験を経て、精神的に立派な大人の男となったキリクは、孤独ではなくなったのだ。宝石のようにきらめく、アフリカの満開の花の中で。そして、キリクは、敵であった魔女もまた、孤立から救い出した。世界を相手に意地悪(キリクのことばを借りれば)し、実際以上に、こわい存在に見せることで、人々を支配してきたカラバは、人々を威嚇するためにも、きんきらきんの宝石ずくめでいることが必要だった。しかし、彼女が一人の美しい女に立ち戻ったとき、宝石は、自分自身と彼女を愛する人たちのために、新たな輝きを放ちはじめた。
次々とキリクにふりかかった試練の数々は、子どもが大人になるための儀式、通過儀礼だったような気もする。思ってみれば、わたしたちだって、キリクほど英雄的ではないにしろ、自分自身の冒険を経て、大人となっているのではないだろうか。覚悟と孤独。そして、癒し。わたしたちが「キリク」という物語にひきつけられるのは、そんな共感からかもしれない。
岩田裕子